例えば「レディ・ファースト」って、ジェンダーレス社会には反する?子供にはどう教えればいい?
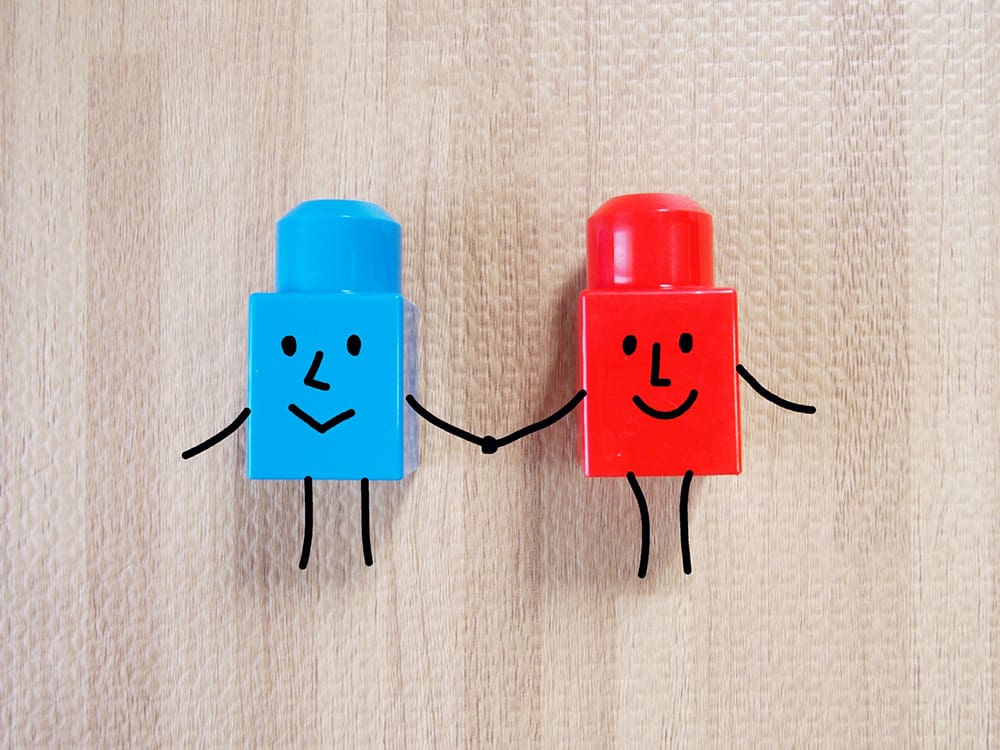
単純に「男子だから」で片づけて許していていいのかしら? ジェンダーフリーが問われている今、子育てへの疑問を弁護士・太田啓子さん、脳科学者・細田千尋さんに伺いました。

弁護士・太田啓子さん 小6と小3男児の母。離婚問題や相続問題、セクハラ・パワハラ事件などに多く関わる。数々の経験を基にした、ジェンダーにまつわる投稿が反響を呼ぶ。息子が最近、読んでいた世界偉人伝のマンガもジェンダーが増え、変わってきたと実感している。

脳科学者・細田千尋さん 医学博士。脳科学者・認知科学者。東京大学大学院総合文化研究科特任研究員、帝京大学戦略的イノベーション研究センター講師、東京医科歯科大学血管内治療科非常勤講師。脳から個人の能力や特性を推定、効果的な能力開発法を研究。2男1女の母。
Q.1 男子は女子よりも肉体的に強くあるべきだと思うのですが、そんな考え方も間違いですか? ジェンダーレ スの社会に反しますか?

弁護士・太田啓子さん
「男子は肉体的に強くあるべきだ」というのが問題なのは、その「べき」と思うあり方から外れた男子、女子への態度次第。肉体的に強くない男子が委縮したり、肉体的に強い女子が自分の個性を肯定的に捉えられなくなるのはよくない。単に「肉体的に強い男性が好き」のみであれば問題ないのでは?

脳科学者・細田千尋さん
男子は〇〇であるべきだ、というのは、すべてジェンダー問題に関わると考えます。「男子が強く」は、守る対象「弱者=女性と子供」という構図。領土争いの時代ではないので、身体的に強く、弱者を守る、は今の社会で成立しないのでは? 男女関係なく、社会を支える一員として心身の強さが求められていると思います。
Q.2 「レディ・ファースト」がわかる男子に育ってほしいと思います。それもジェンダーレスの社会に反しますか? 保守的な考え方ですか?

弁護士・太田啓子さん
「レディ・ファースト」の意図次第かと。「女性は男性に守られるべき存在」という考え、女性は男性よりも弱く庇護を要する存在、という考えが根底にある場合は、やっぱり好ましくないのでは。女性を尊重し敬意を払っての行動で、お互いに対等な関係性の中での行動であれば、いいのではないかと思います。

脳科学者・細田千尋さん
息子に「レディ・ファースト」がわかる男子に育ってほしいとは全く思いません。一方、人として、細やかな気遣いと思いやりがある男性になってほしいとは思います。これは娘に対しても一緒。結局、人として、一緒にいる人が心地よくいられるように気遣いと思いやりをすることが重要。性別は関係ない。
Q.3 「やっべえ」とか「マジかよ」という言葉遣い。男の子なら許すけど、女の子には使ってほしくない。これもおかしいですか? むしろ、女の子にも許すべきでしょうか?

弁護士・太田啓子さん
親としては悩ましい……。でも、男女で異なる基準を適用するのは、私自身は好ましくないと思っています。男の子だから暴力的な言葉遣いも容認する、ということを私はしません。他人を傷つけるようなことを言わなければいいのですが、子供たちはゲームでは言っているので、その都度注意し疲れます(笑)。

脳科学者・細田千尋さん
ここにも男の子ならいいけれど、という根拠のないジェンダーバイアスが……。この考えが子供に与える影響は大きい。男の子にもこのような言葉遣いはしてほしくなく、小さな頃から綺麗な日本語を覚えることは習慣づけて。綺麗でない言葉遣いは後からできる一方、綺麗な言葉を日常で使うのは案外難しいものです。
Q.4 色と性差について。男の子は「青」を選び、女の子は「ピンク」を選びがちです。 親が押し付けているわけではないのに、子供にはそのような傾向があります。なぜでしょうか?し付けているわけで

弁護士・太田啓子さん
人が成長する過程で、自分のアイデンティティを確立する際〝自分がどういう集団に属するか〟を意識することがあると思っています。自分は「女の子」という集団で、世間で「女の子」は「ピンク好き」というコードのようなものを理解すると、自分がその集団に属しているということをアピールしたくなるんじゃないかと。

脳科学者・細田千尋さん
ジェンダーバイアスの影響が強いと思います。妊娠中に性別がわかると「女の子はピンク」「男の子は青」と母親や周囲が揃える。息子たちも最初、黄色やピンクを好んでいたのですが、4歳あたりから「僕は青、男の子は青、ピンクは女の子」と言うように。園生活で、子供はそのような意識を持ったようです。
Q.5 「鬼滅の刃」は、背景や考え方が保守的で、子供の教育上よくないという意見があります。どう思われますか?

弁護士・太田啓子さん
「教育上よくない」とは思いませんが、「長男だから」「男は耐えろ」などのセリフは大正時代の設定とはいえ、今も「男は云々」と言われているので少しモヤモヤが。しかし子供たちが「昔の価値観に基づくセリフ」と理解して読めばいいと思います。

脳科学者・細田千尋さん
かつては「ちびくろサンボ」も差別的だと問題になりましたが、いつの時代も教育上よくないと指摘されるものはある。子供たちには、どこがよくなくて、それはなぜか? といった思考を含め、多面的に見る習慣を持ってほしいと思う。
Q.6 戦隊もの、ヒロインものなど、おもちゃで分けることは、小さい頃に男女は違うと植え付けてしまうことになる?

弁護士・太田啓子さん
大人が「あなたは男の子だから、このおもちゃね」と性別によって分けることは好ましいとは思いません。いろいろなものに触れながら成長できるように、男の子にもあえてプリキュアを見せる機会を作るくらいのほうがいいのでは。

脳科学者・細田千尋さん
おもちゃがジェンダーバイアスを生むという研究成果は、古くからたくさんの報告があります。その背景からか、以前より戦隊ものを好む女性の割合も多いと感じます。周囲の「男子だから」という発言行動が最も影響するのではないかと。
撮影/吉澤健太 取材/東 理恵 ※情報は2021年3月号掲載時のものです。
