何が本当で何が偽情報?溢れる情報と上手に付き合う方法<情報リテラシー>

人類史上最大量とも言われる情報の洪水の中、押し寄せる情報に日々曝される私たち。体のために栄養をバランスよく摂ることは心がけているけれど、心の健康や知性を育む情報の摂取バランスは偏っているのかも? 情報とどう付き合うべきか、有識者にお話を伺いました。
こちらの記事も読まれています
▶︎青木裕子さん「本が読めない!育児中ママにこそすすめたい爆笑エッセイ」【新連載】
私たちを幸せにする
「情報リテラシー」

専門家が大切にしたい【情報リテラシー】を解説!
Q. あふれる情報の中で、何が正しいかわからなくなり不安…
A. すぐに結論を出さない。情報を宙に浮かせておく勇気を
何かが起こった時、すぐに誰が悪い・何のせいだと結論を出したがる傾向が、これを読んでいるあなた自身にもありませんか?わかりやすい答え=アンサーを求める気風をアンサーカルチャーといい、今の社会に満ちているように思います。手短に結論を出してくれるショート動画や切り抜き動画で、ついわかった気になる。明解な言説はインパクトがあって広まりやすい。でも、物事って簡単に白黒つけられるほど単純じゃないですよね。その情報、本当なの?偏ってない?と不安を感じているなら、その注意深さはとても大切。維持してほしいと思います。
例えば子どもの受験についても玉石混交の情報があふれています。ネット上では経験者の親やどこかの塾の講師や卒業生など、情報発信をしているいろんな人がいますが、まずは鵜呑みにしないこと。一次情報から当たるのが基本で、志望校に足を運んだり、通っている塾で聞いたり、ママ友と話したりして得た信頼度がさまざまな情報と少しずつ照らし合わせて、自分で丹念につぎはぎをしていく作業を怠らずやる。面倒だし時間がかかりますが、情報に呑まれないためには結局これしかありません。その結果、よくわからない情報が手元に残ったら、それはわからないまま宙に浮かせておこう、とする勇気や諦めが必要。すぐ判断しない、他の可能性があるかもしれないと絶えず思っておく。そうして情報を保留しておくと、後日真偽がわかる新情報が入ってくることがある。その時、すぐに鵜呑みにしなくて良かったとか、やっぱり正しかったんだ、とか思えばいいわけで。受験という切羽詰まった状況で焦ってしまうのはわかるのですが、結論を急がない大らかさ、曖昧なものを置いておける余裕を持ちたいですね。
Q. 偏った情報に呑まれて、自分自身がおかしな判断をしそう
A. 対面で信頼し合えるソーシャルキャピタルを大切に
インターネット上ではアルゴリズムによって、興味がある、共感できる情報ばかりが集まるフィルターバブルと呼ばれる環境が作られます。またSNSで好きな人・自分と似た人をフォローすることで自分にとって好ましい情報ばかりに触れる=選択的接触を行うようになり、見る情報、交流する人が偏るように。タイムラインは知らず知らずのうちに自分と似た意見であふれるようになります。たとえ世の中ではごく一部の意見でも、自分には多数派のように見えてしまう、この状況がエコーチェンバーです。
そうなると例えば、健康にいいとSNS上で絶賛されているものを試してみようとして、実はマルチ商法だった、なんてことに遭遇したり。美容医療情報を日々眺めているうちに、顔にメスを入れることに躊躇のないような人たちのポストばかりが目に入って、当たり前に思えてきたり。これには、何か決断をする時に対面で「買っていいかな?」「鼻高くしたいんだけどどう思う?」と本音で自分の欠点についても隠さず相談できる人を普段から作っておくことに尽きると思います。閉鎖的で没入的なインターネットから得た情報について隣にいる夫・ママ友・同僚と話して、自分のタイムラインとは違う価値観に触れることも大切です。「ちょっと待って」「大丈夫?」と声を掛け合える人の「より広いネットワークという財産」=ソーシャルキャピタルが築けていれば安心して情報を扱えるのではないでしょうか。
Q. 偽情報に騙されないためには?
A. それを発信する理由、意図は?発信者の背景を想像
少し前、高級ブランドらしいダウンコートを着たローマ法王の画像が「こんなブランド物を着てやがるんだぜ!」と主に海外で大拡散されたのをご存じでしょうか。これは実はAIの作ったディープフェイク画像で、偽情報でした。このようなことは、最近よくありますね。特にSNSで注目を集めることが金銭的収入に繫がるようになり、インパクト重視で発信された偽・誤情報は後を絶ちません。さらに日本の場合、日本語が少数派言語である以上、SNSプラットフォーム側での情報の監視や排除=コンテンツモデレーションは、英語圏より後手に回っているのが現状です。
であれば、受取り手が情報に出合った時に鵜呑みにせず、発信者の意図を想像することが必要になってきます。目立って承認欲求を満たしたいのか、インプレッションや広告収入目的なのか、単なるいたずらやパロディか。ん?と思う情報に出合ったら、発信者のプロフィールや過去の投稿まで遡って確認するクセをつけましょう。例えば選挙の時、ある候補者の印象を上げる情報がたくさん流れてきて、発信者をよく見てみたらその多くがフォロワーゼロだったり、一昨日できたばかりのアカウントだったり、みたいなことも実際に国内外で起こっています。内容が完全な噓ではなかったとしても、疑うべき情報だと気づけるはずです。ただ、どんな偽・誤情報も絶対に許さない!と肩肘張るのも疲れてしまいますよね。立ち止まって背景を考えることは習慣にしつつ、多少は清濁併せ呑む覚悟でいろんな情報と付き合っていく、そんな自分も客観的に絶えず疑う。そういった逞しさは必要な時代かもしれません。
Q. なるべく異質な情報に触れるために、何ができますか?
A. 自分にとっての“情報的インフルエンサー”をフォローしてみては
VERY読者世代は仕事や育児の日常に追われ、自分の興味とは違う情報を能動的に取りに行く余裕はなかなかないのが現実だと思います。それならまず、日頃眺めるSNSで、信頼できる情報のセレクトショップみたいな発信者をフォローするところから始めてみては。発信者によってやはり意見は偏りますから、なるべくバランスに気をつけて複数フォローしておくといいかと思います。例としておすすめを挙げるなら、teenVOGUEというティーン向けの情報サイトは日本のメディアが伝えないようなニュースが多く掲載されています。SNSアカウントもあって、英語ですがブラウザの翻訳機能を使えば日本語で読めますよね。ファッションやセレブの情報が並ぶ中に社会的な記事が混ざっていて、この切り口がなかなか敏感です。
例えば、Y2Kファッションとしてロザリオを身につけるのが流行った時。『ファッションとしてのロザリオ:数珠をアクセサリーとして身につけてはいけない理由』という記事を出してトレンドを諫めていたのも興味深かったです。自分に興味のある話題に近いところから、頼りになりそうなあなただけの情報源を少しずつ開拓していく。自分のセンサーをなるべくあちこちに向けられる仕組みを作っておくことで、情報的体力みたいなものが少しずつ鍛えられてくるはずです。
数秒あればAI生成できちゃう
画像をAIで加工してみたら…

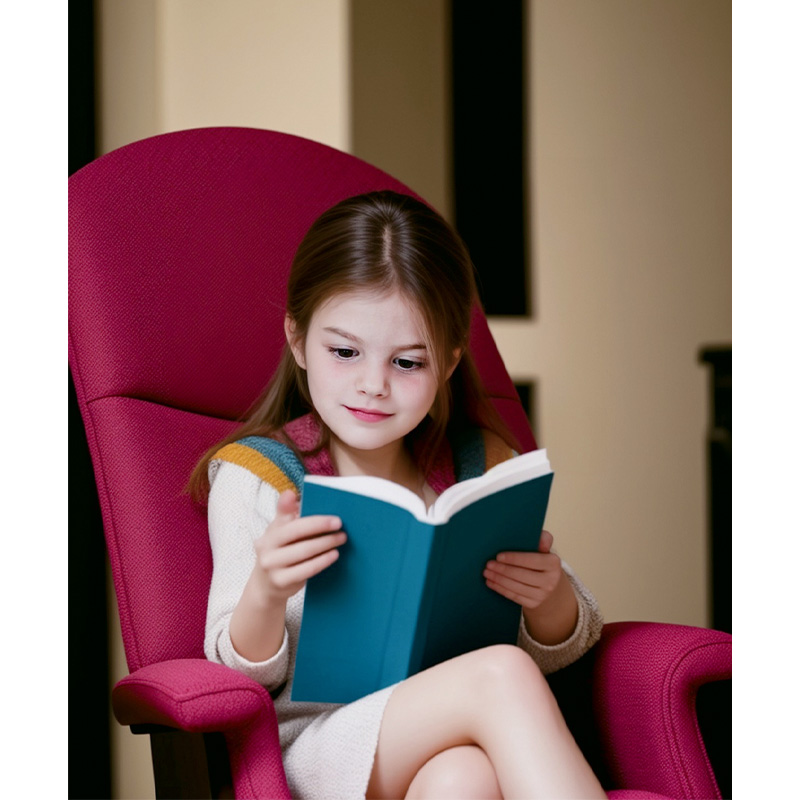

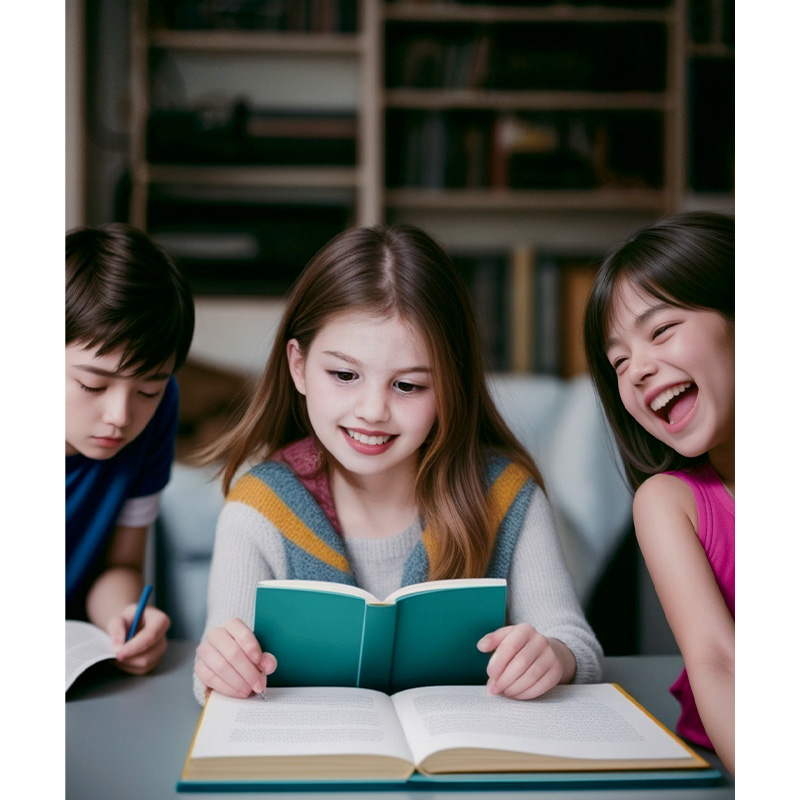
現代の「情報リテラシー」を理解するための用語6選!
その意味を正しく知っていますか?
社会現象・メディア現象の用語6選
アンサーカルチャー
物事が起こるとすぐに、誰・何のせいなのか探したり、対立構造を煽ったりして、わかりやすさを求める気風。「断片的な短い情報で決めつけず、時間をかけて本当の答えが出るのを待つことのできる人が増えると、偽・誤情報に強い社会になっていくと思います」(奥村さん)。
エコーチェンバー
SNSなどで、自分と似た意見や思想を持った人たちと集まりコミュニケーションを続けることで、特定の価値観が増幅し、自分たちは間違いない!と信じ込んでしまう現象。過熱する受験による教育虐待や行きすぎたルッキズム、マルチ商法など、現代社会の問題とも無関係ではないかも。
フィルターバブル
インターネット上での個人の興味や検索履歴をアルゴリズムが分析し、好みを学習することで、同じような情報や意見ばかりが提供される現象。一度ダイエットについて調べたら、しばらくダイエットの広告や投稿ばかり出てくる!なんてこと、よくありますよね?
ソーシャルキャピタル
人々の信頼関係や人間関係などの社会的なネットワークを、価値あるものとみなす概念。「要するに、何かあった時に来てくれるような人がいるかどうか。お節介なご近所さんをなかなか見かけなくなった現代、自分でそういう人を確保しておく必要がある。その点では厳しい時代です」(奥村さん)。
コンテンツモデレーション
インターネット上の不適切なコンテンツを監視し、ユーザーの目に触れにくくしたり、最悪削除やアカウント停止まで行うような仕組み。「例えばTikTokは日本人のスタッフやジャーナリストが米のファクトチェック機関と連携して偽情報を管理するなどの対応を行っていることを公表しています」(奥村さん)。
情報的インフルエンサー
自分の興味に近く、かつ社会との接点を紹介してくれるような人・媒体のこと。「例えばVERYの連載陣をフォローしてみて、それでも彼らにも伝えきれない情報や偏りがあることを発見し、そこをどう埋めていくかを考えることが大切です」(奥村さん)。
Profile

武蔵大学社会学部教授・ジャーナリスト
奥村信幸さん
1964年生まれ。上智大学大学院修了。テレビ朝日で「ニュースステーション」ディレクターなどを務める。海外での研究、取材等を経て’13年より現職、専門はジャーナリズム。ファクトチェック・イニシアチブ(FIJ)理事としても活躍し、ニュースの信頼向上に取り組む。
あわせて読みたい
▶︎元ギャル誌モデル・近藤千尋さん&宮城舞さん『あの頃培った“楽しさ追求マインド”は今も活きている』
▶︎『子育て短歌』にハマるママ続々!日常を切り取るママの想いに共感
▶︎子どものお小遣いに『誰かのために使わないと1年後に消える500円』の新提案!
取材・文/西原章 編集/中台麻理恵
*VERY2025年5月号「私たちを幸せにする情報リテラシー」より。
*掲載中の情報は誌面掲載時のもので、変更になっている場合や商品の販売が終了している場合ございます。
