親族からの難関校の期待、子の円形脱毛症…親の未熟さがあぶり出される夏【中学受験小説連載】
【前回まで】合格判定模試で一年前からグンと偏差値を伸ばし、自由が丘国際が射程圏内という娘・沙優に高揚感を覚える美典。しかし、「将来は類くんのママ・エレナさんのようなキャスターになりたい。ママは何になりたかった?」と聞かれ、自身は夢がないことに気づく。一方、玲子は浮気発覚以降、夫・翔一が家に帰らぬ中、同級生の家に赤ちゃんが生まれることを羨ましがる莉愛に「妹が欲しい」と言われ……。
▼前話はこちら
「ママは何になりたかったの?」母たち自身の幸せのカタチとは…【中学受験小説連載】
【第十八話】 小6・7月
床に転がっていたサッカーボールをスリッパのつま先で引き寄せたりしながら相槌を打っていた玲子だったが、「で、つまり?」と電話の向こうの声を遮って言った。
「悪いものじゃなかったってことよね?」
「ああ、まあ、そういうことね」
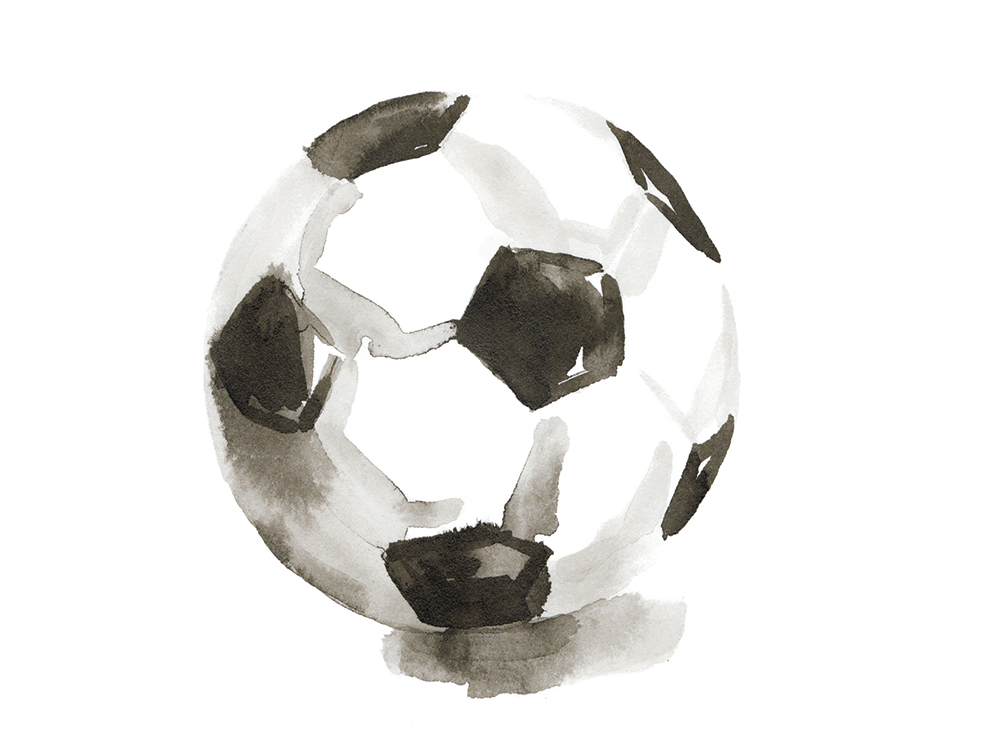
実母である純代がそう言うので、玲子はほっとする。咳が続いていた父、孝夫の肺に影のようなものが見つかり、再検査となっていた。最悪の想定もしていたので安堵した。
「いろいろ出てくる年齢だし、しっかり診てもらえてよかったじゃないの」
さっさと切り上げたくてまとめるように言ったが、それでね、と純代は話を続ける。
「お母さんも不安になって、健康診断を受けてみたんだわ。そうしたら高血圧だって言われちゃって」
「いくつだったの?」
「上が155で、下がえっと83? 84だっけ」
「たしかに高いね。薬はもらったんでしょう? それを欠かさず飲んで、あまり気にしすぎなくてもいいから。塩分控えめにして、一日三十分くらい歩くようにしてみて」
看護師らしく説明していると、つま先で遊んでいたサッカーボールが向こうに転がっていく。真翔が四年生の時に買ったボールだが、ほとんど汚れていない。慶應の入試で行われる体育実技の試験対策用に購入したもので、家の中でしか使っていないからだ。
そろそろ真翔が学校から帰ってくる。今日は塾も家庭教師もない日だから、だらだらさせないようにしなくては。
純代の話をまともに聞きもせずに適当な相槌を打っていたが、「ねえ、玲子。どうしたらいいんだろうね」と言うのが聞こえた。
「はっ、何が?」
「だから、今回のことで考えたってことよ、お父さんが介護になったら、どうしたらいいんだろうかね」
ああ、そういうことか。
純代の話は朝方に見る夢みたいなもので、内容があるようでない。ただ相槌を打ってやるだけでも疲れてしまう。
「そうなったらプロに頼むのが一番よ。でも、お父さんの咳も止まったんでしょう。ひとまず大丈夫じゃないの」
「あんたも他人事よね。あんただけじゃない、みんなそう」
「みんなって」
「諭も勇も」
純代は拗ねたように声を歪ませる。
「諭お兄ちゃんはたまにそっちに行ってるの?」
長兄の諭は札幌市内に住んでいて、その下の兄、勇は福岡に住んでいた。
「正月に来たきりよ」
母のふくれっ面が目に浮かんだ。諭の家は実家から車で十五分ほどの場所にあるが、母と兄嫁の関係がよくないせいで、兄夫婦が足繁く通っている様子はなかった。勇にいたっては、新卒で入った会社が福岡勤務で、その後に福岡本社の会社に転職、地元の女性と結婚して家も買っているので、玲子以上に実家と距離ができていた。
「実際のところ、あたしだって北海道と東京を行ったり来たりできないし、プロの力を借りるしかないじゃないの。家で難しくなれば、施設を探せばいいと思う」
玲子がそう言うと、スマホの向こうで鼻息が聞こえる。笑ったのか、むかつかせたのか、読み取れない。
「あたし、そんなに子育てに向いてるタイプじゃなかったのよ。小さい子供は苦手だったもの」
「ああ、そう」
「でもね、どうしても娘がほしかったの。娘はそばにいてくれるものだと思っていたから、三人目を産んでみようって」
なるほど、どうやらむかつかせたようだ。はあ、と玲子はわざとらしくため息をつく。
「お母さん、どうすればいいわけ? 月に十万円も仕送りしているのに、それでも足りない? だったらお兄ちゃんたちからももらってよ」
「お金のことじゃないの。仕送りしてくれているあんたと翔一さんには感謝してんのよ。それとは別の話よ。そばにいられなくてもいいから、話くらい聞いてくれてもいいじゃないの」
「だから、聞いてんじゃん。お父さんのことが不安だって言うからプロに任せたらって言ったら、他人事だって一蹴されて。じゃあ、どんなふうに言ったら満足すんの?」
「もういいわ」
涙声でそう言って、母は通話を切った。
もう何なのよ!? 大人なんだから、ちょっときつく言われたくらいで泣かないで。玲子はぐったりしてスマホを棚に置いた。
離れたところに住んでいる母に優しく接してやりたい。母の話だって聞いてあげたいと思っている。その気持ちとは裏腹に、性格があまりに違っている純代にはいちいちストレスを感じてしまう。正直、義母よりも実母のほうが面倒臭い。
インターフォンが鳴った。モニターに真翔が映っている。モニターのボタンを押して玄関ドアを開錠すると、ほどなくして真翔がリビングに入ってきた。
「おかえり。暑かったでしょう」
キッチンカウンター越しに真翔に声をかけて、玲子は冷蔵庫から麦茶を取り出した。
「お母さん、あのさ」
ランドセルをソファの上に放り出し、真翔はいつになく真面目な表情でこちらにやって来た。
「どうかしたの?」
麦茶の入ったグラスを差し出すと素直に受け取り、やはり喉が渇いていたのか一気に半分ほど飲み干した。
「俺ってさ、慶應以外にどこの学校を受けるんだっけ?」
「慶應以外? どうしてそんなことを訊くの?」
ドキッとした。毎日のほとんどを受験勉強に費やしているというのに、これまで慶應以外の志望校について彼が訊いてくることはなかった。さすがにこの時期になれば、現実的にいろんな考えを巡らせるようになったのだろう。
「友達、いろいろ学校を見学に行ってんだよ、開煌中とか麻見谷中とか」
「まーくん、御三家を受けたいってこと?」
玲子が驚きのあまり声を裏返らせると、違うよ、と真翔は否定した。
「いろいろ見て決めたほうがいいんだろうなってこと。慶應以外にも受けるんだよね? たとえば目黒工大附属とか? いまからでも慶應以外の学校を見学したいんだけど」
「もう六年生の夏よ。そんな時間ないでしょう。学校見学なら五年生のうちにしたじゃない」
「慶應と目黒工大附属だけじゃん」
「十分でしょう。だってまーくんは慶應の普通部か中等部か湘南藤沢、その三校のうちのどこかに入学するんだから。通う可能性がないところを見てもしょうがないじゃない」
「もしもだよ? もしもその三校がダメだったら、どうするの? こんなに塾ばっかり行ってんのにさ、公立中になんて行きたくねえから!」
「いまから悪い想定をしてどうするの。とにかく合格するためにひたすら頑張るだけでしょう」
「慶應に行きたいよ! でも、他はなし? 俺って自分で行きたい学校を選べないわけ?」
玲子は言葉に詰まる。正直、真翔に選択権があるなんて考えたこともなかった。思わず手元が緩んで、泡だらけのデュラレックスのグラスが滑ってシンクに転がる。
「真翔にとって一番いいのは慶應だろうって思っているから、勧めているの。おじいちゃんとおばあちゃんも、期待してくれているし、お父さんだって」
「あーねぇ。はいはい、わかった。俺よりも、おじいちゃんとかってことね」
「そんなことない」
玲子は反論しようとしたが、真翔は二階へと駆け上がってしまう。
そんなことない、けど……。
その先に続く言葉を、玲子は見つけることができなかった。思春期に入ってきたのかな。ゲームができれば楽しそうにしていた息子も、だんだんと難しくなってきた。
ああ、ビールが飲みたい。玲子は泡のついた手を洗ってタオルで拭くと、エプロンのポケットからスマホを取り出す。この時間なら、美典はバイトが終わっているだろうか。
—
駒沢オリンピック公園の噴水とモニュメントがそびえる広場に行って、美典は見回す。売店の横に併設された飲食できる一角から、玲子がこちらに向かって手を振っているのが見えた。
「いつも急に連絡してごめんね」
「ちょうどバイト先を出てスマホを取り出したら、玲子さんのメッセージがピコンって入って、ちょっと運命感じちゃった」
玲子がすでにビールを飲んでいるので、美典も売店で買う。玲子の向かいに座り、おざなりに乾杯した。

「誰かに愚痴りたくなると、美典さんの顔が浮かぶんだよね。あたし、美典さんと出会う前はどうしていたんだろう。たいしたストレスもなくやれていたのかしらね……思い出せないわ」
「そう言ってもらえると嬉しいよ。しかも仕事終わりに、オープンエアで飲むビールのうまいこと」
しみじみと美味しさを嚙み締めるようにビールを飲んだ。そんな美典を見て、玲子はほっとしたように笑った。
「美典さんといると、なんか楽なんだよね。あたしみたいな薄っぺらな人間に付き合ってくれて、あなたって稀有な人よ」
「玲子さん、全然薄っぺらじゃないでしょう」
「見せかけの、はりぼてなんだよ。美典さんにもカッコつけて来たけど、もうどうでもよくなってきちゃったな」
「カッコつけてきたの? っていうか、玲子さんはカッコいいんだから、見せかけじゃないよ!」
玲子が素敵なのは揺るぎない真実だ。そういう気持ちで美典が見ていると、玲子は観念したようにため息をついた。
「もう言っちゃっていい?」
「えっ? 何を?」
「美典さんには全部ぶちまけたい。いい?」
「いいよ。ぶちまけてよ」
これまでも玲子にはいろいろぶちまけられてきたと思っていたが、まだあるのかと、美典はどきどきした。
「真翔ね、慶應の幼稚舎を受けて落ちているのよ」
玲子はそう言った。
「ああ、そうなんだ」
「いま、美典さん。ああ、そうなんだって言ったでしょう。あたしが言ったことにたいして驚くわけでもなく、ああ、そうなんだって」
いったい玲子は何が言いたいのだろう。よくわからないまま、だね、と美典は頷いた。
「でも、真翔が幼稚舎に入れなかったということが、いまのあたしを苦しめる元凶なのよ」
「元凶? そうなの?」
「神取家は慶應一家で、義父は大学から慶應で、義父のお兄さんも慶應。翔一と翔一の姉は幼稚舎から慶應。翔一は普通部から医学部へ、お義姉さんは経済学部。外資系の医療メーカーでバリバリ働いていたけど、商社マンの旦那さんについて行って、ここ数年はニューヨークに住んでいるの。義姉の旦那さんは慶應の理工学部。義姉の娘はもちろんニューヨーク慶應。義母の弟も慶應で」
「ちょっと待って、すごいね。『華麗なる一族』みたい」
美典は思わず笑ってしまった。が、玲子は真顔のままだ。笑うところではないのだと察して、緩んだ頰を引き締めた。
「この世の幸せは人脈次第。慶應に入ることで茫漠な人脈と繫がれる。生きていくうえでの、大いなるメリット。それがあの家の大前提。だから、神取家の孫である真翔と莉愛は幼稚舎から慶應に入れなくてはならない。嫁いだあたしのノルマみたいなもの」
「大変……だね?」
「すごく大変! 地方から出てきて小学校受験はおろか中学受験だって縁遠かったあたしには、荷が重すぎる。それでもたぶん、大丈夫だろうってたかを括っていたの。だって翔一は幼稚舎から医学部だし、幼児教室の先生も太鼓判を押してくれていたし。でも結果は……」
「小学校受験こそ、何を基準にしているのか見えにくいところがありそうだものね」
「ただ、気になっていたことがあったの。夫は医学部時代に痴情のもつれで警察沙汰になったことがあったって言ったよね?」
「新宿御苑のつばき、でしょ?」
そう、と玲子は頷いた。
「夫が過去に起こした不祥事が、慶應の卒業生のデータに残っているのかわからないけれど、そのせいで真翔が不合格になったんじゃないかって勘ぐったりして」
「だけど、莉愛ちゃんは合格をもらっているよね?」
「莉愛はあきらかに利発だったからね。幼児教室でもダントツでできる子だったし、多少のバツも撥ね除けられたんじゃないかな」
「なるほどね」
「とにかくそういうこともあって、余計につばきが憎いの。そして、どんなことがあっても真翔を中学受験で慶應に入れなくちゃいけないというプレッシャーがあたしの肩に乗っているわけ」
それで元凶と言ったのか。ようやく美典も理解できた。
「そりゃ、ビールを飲んで愚痴りたくなるよ」
美典が労うように言うと、はあ、と玲子は伸ばしていた背筋を丸めた。
「ああ、ちょっとスッキリした。誰かに話せるってだけで楽になれるわ」
「いつでも話してよ。前にも言ったよね。たいしたアドバイスなんてできないけど、聞くだけならできるんだから」
「ありがと」
「ねえ。慶應って、何校かあるよね? どこがいいの?」
「翔一の母校である普通部が第一志望だけど、中等部でも湘南藤沢でも合格をもらえるなら」
「慶應以外は受けないってこと?」
「さっき真翔ともその話になって、あの子は他の学校にも興味があるみたいなのよ。でもいまは、慶應以外のことを考えてほしくない。というか、あたしが考えたくないの。この時期になって何を言っているんだって感じだけど、マイナスのことを口にしたくないのよ。いまあたし、言霊信仰をしているから」
「コトダマって……あの言霊?」
「自分が口にした言葉のとおりの現実を引き寄せるって、ある人から聞いて、そういう力ってあるだろうなと思って。お金のかかることではないから、信じてみることにしているの」
そう話す玲子の顔が、いつもどおりに華やいで、美典はホッとした。玲子の心が軽くなるのなら、どんなことでも取り入れてほしい。玲子がすっきりしたようにビールを飲み干すのを見て、美典も飲み干した。
「この場所いいね。今度はエレナさんも誘いたいな」
「彼女、忙しいしテンパってるんじゃないかな。類くんのアレルギーが悪化して、うちに来てくれたみたい。ナースから聞いたの。受験のストレスじゃないかしらって」
ストレスでアレルギーも悪化するのか。
「沙優も抜毛症がおさまるといいんだけど」
「きっと受験が終われば完治するはずよ。それまではあまり気に病まないようにして……美典さんも」
「翔一先生に診てもらうの、一度は躊躇したんだ。何となく玲子さんに知られたくないって気持ちがあって、違うクリニックを受診しようかなって」
「そうだったの」
「けっきょく確かな治療を受けたかったから翔一先生を受診して、そうしてよかったんだけど……どこかで、子供にストレスをかけているような負い目があった。だから玲子さんに知られたくないって思ったんだよ。ずるい、ひどい母親だな」
口に出したせいか、涙が溢れてきた。自覚している以上に自責の念があったのかもしれない。美典さん、と玲子が肩に手を添えてくれて、ますます涙が出てきた。
「中学受験って残酷よね、親の未熟さまでもが炙り出されるんだから」
「まったくだよ」
「受験終わったら、三人でパーッと飲もう」
玲子も涙声になり、そう言った。
「そうだね。三人でね」
中学受験が早く終わってほしいような気もするし、本番が迫ってくるのが怖いような気もする。だけど、いつかは終わる。二月一日まで、もうすぐ半年を切ろうとしていた。
(第十九話をお楽しみに!)
イラスト/緒方 環 ※情報は2025年8月号掲載時のものです。
おすすめ記事はこちら
▶学校に行きたがらない娘さんに、歌手・畑中葉子さん(65)が取った行動とは…
